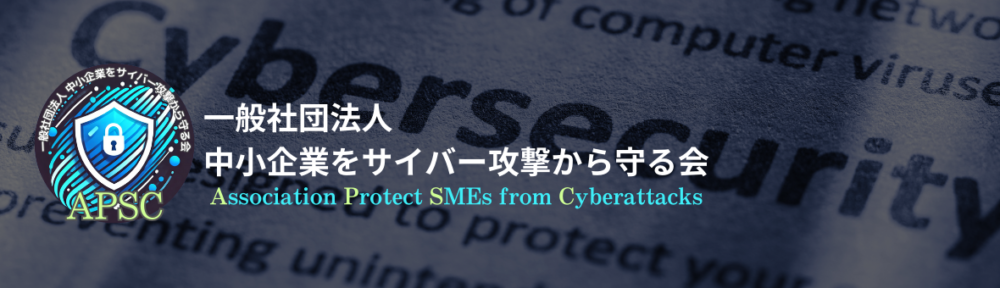大学を狙った不正アクセス事件から学ぶ ― 中小企業も他人事ではないサイバーリスク
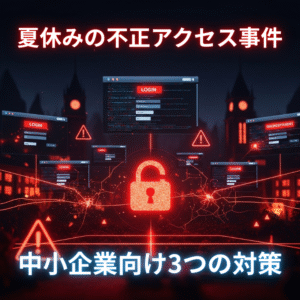
8月も後半、夏休み期間を利用して大学や研究機関がオンラインシステムを稼働させ続けている中で、不正アクセスによる被害が報告されています。直近では、関西の某大学で学内のポータルシステムが侵入され、学生や教職員のアカウント情報が一時的に外部に流出した可能性が指摘されました。幸い、金銭的被害や大規模なシステム停止には至りませんでしたが、数千件単位のログイン情報が対象になったとされています。
教育機関は狙われやすい存在です。研究データや学生の個人情報など、価値のある情報が集中している一方で、利用者が多くセキュリティ教育が行き届きにくいという弱点があります。今回のケースも「使い回しパスワード」や「安易なID管理」が攻撃の突破口になった可能性が高いとみられています。
ここで重要なのは、大学の事件だからといって安心できないということ。中小企業でも、社員アカウントが1つ突破されれば、社内のファイルサーバーやメールシステムに芋づる式に侵入されてしまうリスクがあります。特に近年は「ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)」の被害が深刻で、バックアップごと暗号化されるケースも少なくありません。
中小企業が今すぐできる3つの対策
1. パスワードの強化と多要素認証の導入
複雑なパスワードを設定するだけでなく、ワンタイムコードや認証アプリを併用しましょう。
2. 不審メール対策の徹底
フィッシングメール(偽装メール)は依然として入口攻撃の主流です。不正メール訓練サービスを活用して社員の注意力を高めることが有効です。
3. システムの脆弱性診断
古いサーバーや未更新ソフトは攻撃者に狙われやすいポイントです。定期的な診断で“穴”をふさぐことが必要です。
「大学の事件」は決して遠い話ではなく、どの企業でも起こり得る現実です。今日からでもできることを始め、被害を最小限に食い止める備えをしましょう。