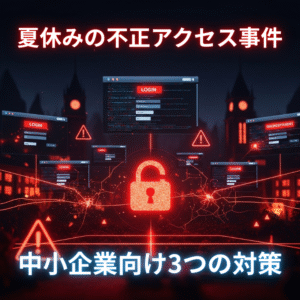中小企業が見落としがちな「社内セキュリティルール」の落とし穴
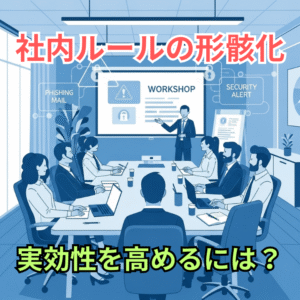
中小企業の経営者の方からよく聞くのが、
「社員には注意するよう伝えているが、どこまでやれば十分かわからない」という声です。
実際、社内でルールを作ったとしても、形骸化してしまい、現場では守られていないことが多々あります。たとえば――
• USBメモリの使用禁止:禁止を掲げても、現場で「ちょっとだけなら」と使われてしまう
• パスワードの定期変更:ルールはあるが、結局「1234」や「password」など形だけの更新にとどまる
• メールの注意喚起:全社員に通知しても、実際に不審メールを見抜ける人は少ない
このような「ルールと実態の乖離」が、サイバー攻撃の入口になっているのです。
なぜルールが守られないのか?
多くの場合、ルールが「現場感覚とかけ離れている」ことが原因です。
たとえば、「USBを全面禁止」ではなく「どうしても必要な場合は申請を出す」など、現実的な運用に落とし込むことが大切です。
また、ルールは一度作って終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。クラウド利用やテレワークの拡大に伴い、数年前のルールが今の働き方に合っていないケースも少なくありません。
実効性を高めるための3ステップ
1. 社員に分かりやすい言葉で周知
専門用語を避け、イラストや具体例を交えて伝える。
2. 定期的な訓練を実施
不正メール訓練やセキュリティ研修を通じて「体験」することで身につく。
3. 仕組みで守る
CheckPoint社のUTMなど、外部からの攻撃を自動的にブロックする仕組みを導入し、「人頼み」の部分を減らす。
特に、社員教育と技術的な防御をバランスよく組み合わせることがポイントです。
中小企業だからこそ、「人」と「仕組み」の両輪を意識したセキュリティ対策が求められます。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
中小企業の情報セキュリティ強化を一緒に進めてまいりましょう!
無料相談はこちら
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/