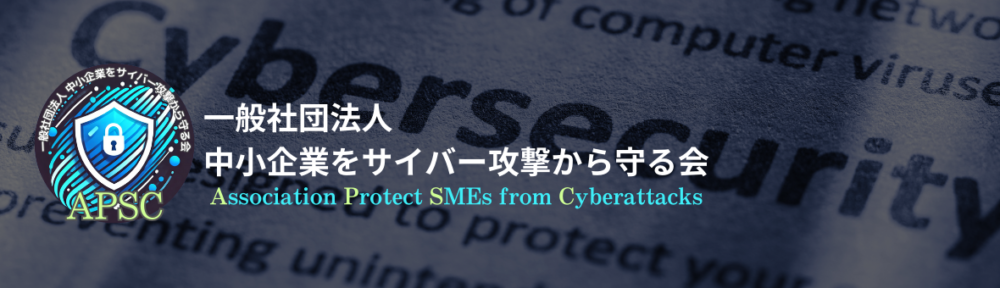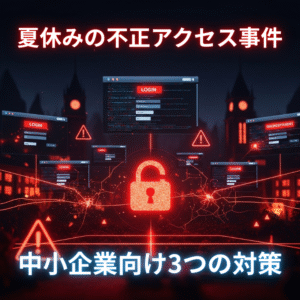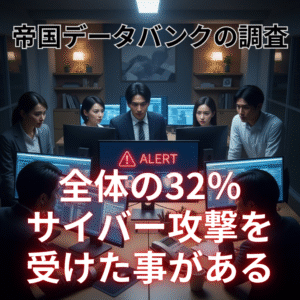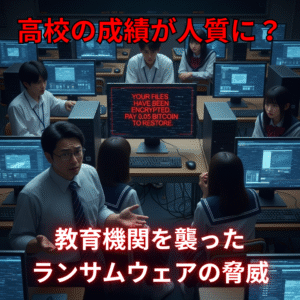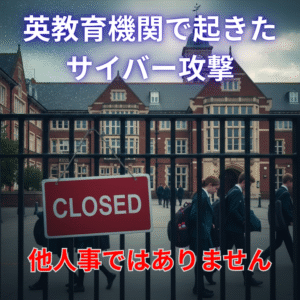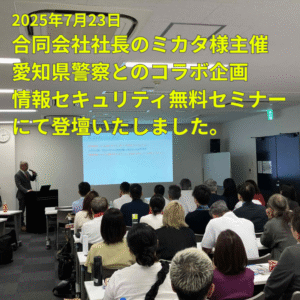“平和”と“デジタルの安全”
~学校も狙われるサイバー攻撃、その実態とは~
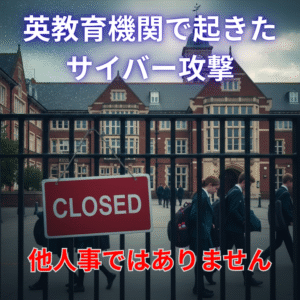
本日8月6日は、広島に原爆が投下された日です。
私たちは、二度と同じ悲劇を繰り返さないようにと誓い、平和への思いを新たにする日でもあります。
そして近年では、“平和”や“安全”という言葉に、少しずつ新しい意味が加わり始めています。
たとえば、サイバー空間における安全。目に見えない攻撃が、私たちの生活や教育の現場にも静かに忍び寄っています。
学校が閉鎖!?海外で実際に起きたサイバー被害
昨年2024年9月、イギリスの「チャールズ・ダーウィン・スクール」という中等教育機関が、サイバー攻撃を受けました。
被害は深刻で、システムが使えなくなり、一時的に学校が閉鎖される事態に。
オンライン授業もストップ。生徒への連絡もままならず、学校運営は完全に麻痺してしまいました。
この事件、実は「特別な技術を持ったハッカーが狙った」わけではありません。
多くの学校や教育機関が抱えている、基本的なセキュリティの甘さが原因のひとつと言われています。
日本の学校や中小企業も、例外ではありません
「海外の話でしょ?」と思いたくなる気持ちもよくわかります。
ですが、実際に国内でも、
• 教育委員会のネットワークが不正アクセスを受ける
• 生徒の個人情報が流出する
• 学校のウェブサイトが改ざんされる
といったインシデントは、年々増えています。
特に、クラウド活用やオンライン授業が当たり前になった今、教育現場も立派な“サイバー空間の住人”。
狙われるリスクは、もはや企業と同じなのです。
じゃあ、どう備えるべき?
最低限やっておきたい対策は以下の3つです。
1. システムやソフトを常に最新に保つこと
2. 不審なメールを開かないよう、教職員や職員に教育すること
3. 外部からの侵入を防ぐセキュリティ機器(たとえばUTMなど)を導入すること
中でもおすすめなのは「不正メール訓練」や「情報セキュリティ研修」。
実際のシミュレーションを通じて、感覚的に学ぶことができるので、効果は抜群です。
最後に
“平和”という言葉には、誰かが守ってくれている「日常の当たり前」が含まれているのかもしれません。
学校が毎日開いていて、子どもたちが安心して学べる環境があることも、そのひとつです。
だからこそ、私たち大人ができる備えは、疎かにしてはいけないと強く感じます。
「中小企業や教育機関の情報セキュリティ強化、私たちがサポートします!」
ご相談や対策のご依頼は、どうぞお気軽にご連絡ください。
無料相談フォーム
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
では今日もセキュアな一日を。