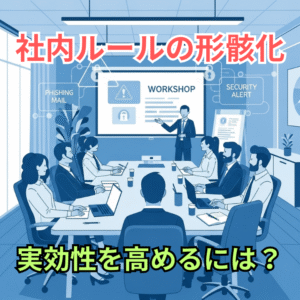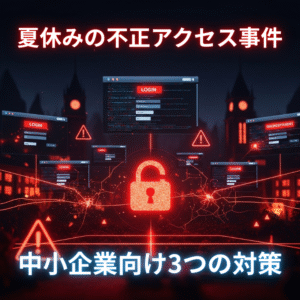「防災の日に考える ― サイバー攻撃にも“備え”が必要です」

本日9月1日は「防災の日」。地震や台風など自然災害への備えを見直す日として広く知られていますが、近年では「サイバー災害」にも備える必要性が高まっています。
実は先月、国内の自治体や企業を狙ったサイバー攻撃の被害報告が相次ぎました。特に目立ったのが ランサムウェア(身代金要求型ウイルス) による被害で、重要データを暗号化され、業務が数日間停止したケースもあります。自然災害と同じく「いつ」「どこで」被害に遭うかは予測が難しく、事前の対策が明暗を分けます。
ここで押さえておきたいのは、サイバー攻撃の「想定外」が日常的に起きているということです。
・取引先を装った不正メール
・AIで自動生成されたディープフェイクの音声や映像
・VPNやサーバーの脆弱性を突いた侵入
こうした攻撃は、中小企業を含め誰もが標的になり得ます。
では「備え」として、何から始めればよいのでしょうか。
まずは災害対策と同じく「基本の3ステップ」を意識することが有効です。
1. リスクの把握
どの資産(サーバー、PC、顧客データ)が守るべき対象かを棚卸し。
2. 対策の実施
UTM(統合脅威管理)を導入し、外部からの侵入や不審な通信を遮断。社員向けにはセキュリティ研修や不正メール訓練で“人の防御力”を高める。
3. 復旧の準備
バックアップの定期実施、インシデント発生時の対応ルールを明文化。
特にUTM(例:CheckPoint社製)は「防火壁」のように外部からの脅威を止める役割を果たします。自然災害で言えば堤防や耐震構造にあたる部分です。さらに、社員のセキュリティ意識を高める研修は「避難訓練」と同じ。どちらも欠かせない備えです。
「防災の日」の今日こそ、会社の“サイバー防災”を見直す絶好のタイミングです。
明日はあなたの会社が狙われるかもしれません。備えあれば憂いなし。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
無料相談はこちらから
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/