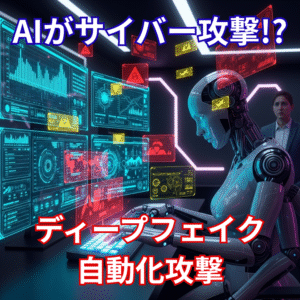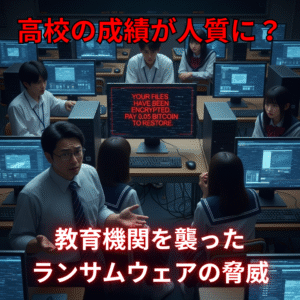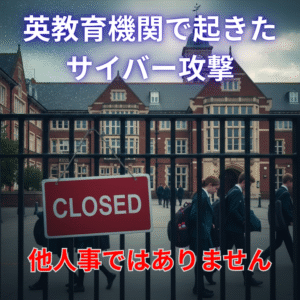中小企業こそUTMを導入すべき理由とその効果

サイバー攻撃は「大企業が狙われるもの」というイメージを持たれる方も多いですが、実際には中小企業が標的になるケースが年々増加しています。理由は明快で、「守りが手薄で侵入しやすい」からです。攻撃者にとっては、大きな魚を狙うよりも小さな企業を数多く攻める方が効率的なのです。
なぜUTMが有効なのか?
UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)は、複数のセキュリティ機能を1台にまとめた“セキュリティの総合パッケージ”です。
• ファイアウォール(不正アクセスの遮断)
• アンチウイルス(マルウェア検知)
• IPS/IDS(侵入検知・防御)
• Webフィルタリング(不正サイトへのアクセス制御)
などが一体化しており、IT担当者が専任でいない中小企業にとって、導入と運用のハードルを下げてくれる存在です。
CheckPoint社UTMの強み
当社が特に推奨しているのが CheckPoint社のUTM です。世界的に信頼されているセキュリティベンダーで、最新の脅威情報を活用しながらリアルタイムで不審な通信を検知します。特に最近増えている 標的型メール攻撃 や ゼロデイ攻撃 にも対応できる点が大きな安心材料です。
導入効果は「安心」と「コスト削減」
「セキュリティにお金をかけられない」という声もよく聞きます。しかしUTMの導入は、もし被害に遭ったときの 復旧費用や信用失墜コスト に比べれば圧倒的に低コストです。
加えて、複数のセキュリティ機能を別々に導入するよりも運用がシンプルになり、担当者の負担も軽減されます。
まずは“相談”から
すべての企業に同じ対策が必要なわけではありません。業種や規模によって最適な設定は異なります。
そのため、まずは自社のネットワークの現状を診断し、必要な防御策を見極めることが大切です。当社では 脆弱性診断やセキュリティ研修 も組み合わせて、無理のない導入をサポートしています。
無料相談フォーム
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
サイバー攻撃は待ってくれません。中小企業だからこそ、手軽で効果的なUTMを活用し、“攻められにくい会社”を目指しましょう。