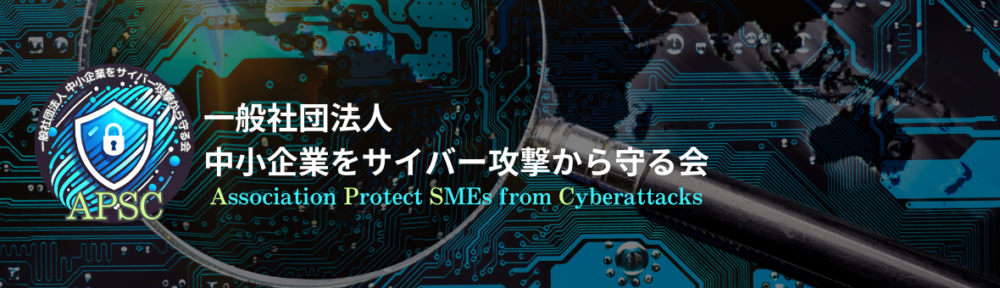12月9日(火)、千代田区岩本町の岩本ほほえみプラザさんにて、警視庁サイバーセキュリティ対策本部の方とのコラボセミナーを開催いたしました。
今回は、募集80名に対して、96名ものご参加登録をいただき、当日は約90名の方々にご参加をいただきました。みなさんとても熱心にお話を聞いてくださり、ご質問もいくつか頂戴いたしまして、大変有意義なセミナーとなりました。
集客にご協力いただきました合同会社社長のミカタ様、合同会社クリアースカイ様には、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。
警視庁様とは、3回目の開催となりましたが、ご用意くださるコンテンツも毎回パワーアップしていて、私も大変勉強になりました。
年内の勉強会スケジュールはこれで全て終了です。
来年は、1月はセミナー開催はお休みをさせていただきまして、2月に北海道警察様にご協力いただき、札幌にてセミナーを行いますので、楽しみにしていてください!
「Uncategorized」カテゴリーアーカイブ
2025.10.11 名古屋にてセミナー登壇
昨日10月11日、名古屋市内にて合同会社クリアースカイ(https://clearsky-japan.jp/)の、IPFSとブロックチェーン技術を使ったサーバー事業についての事業説明会にて、情報セキュリティに関する登壇をさせて頂きました。
ご来場は70名超で、今回はフィシングメールや偽サイトの見分け方、パスワードの漏洩チェック、ランサムウェア最新動向などのお話をさせて頂きましたが、みなさんとても熱心に聞いてくださって、「勉強になりました」「知らなかった!」「これって大丈夫ですか?」など様々なご感想やご質問をたくさん頂きました。
ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。
そして、合同会社クリアースカイのサーバーサービス、もう何度も聞いていますが、とても素晴らしいですね。IPFSなので、単一障害点がないこと、改ざんに強いこと、これだけでもかなりセキュアで安心して利用できると思います。
UIもわかりやすく、一言でいうとGoogleworkspaceの国産版って感じ。セキュアなことに加えて、クラウドストレージには珍しくデータの所有権がクライアント側にあることがとても良いです。
そして、中小企業でも導入しやすい価格設定がまたイイです
次回は10月18日那覇、10月25日大阪と、またご一緒させて頂きます。
お近くの方はぜひお声がけください。
2025.10.09 兵庫県警察とのコラボセミナー実施報告
昨日、10月9日14時より、神戸市内にて兵庫県警察サイバーセキュリティ・捜査高度化センター サイバー企画課の方にご協力いただき、情報セキュリティに関する無料セミナーを開催いたしました。
参加者は約20名。皆さま非常に熱心で、質疑応答では次々と質問が飛び交い、予定時間を大きくオーバーするほどの熱気に包まれました。
セミナーの中では、兵庫県警が対応した令和7年上半期のランサムウェア被害件数がわずか5件という公式データが紹介されました。
しかし、兵庫県警と連携している民間セキュリティベンダーによると、実際には200件以上の出動があったとのこと。
つまり、警察に届出があったのはほんの氷山の一角にすぎず、水面下では想像をはるかに超える被害が発生している現実があるということです。
この数字には、私自身も強い衝撃を受けました。
「うちは小さい会社だから関係ない」と思っている中小企業こそ、最も狙われやすく、また被害を受けても公表しづらい現状があります。
被害の多くが表に出てこない構造そのものが、日本のサイバーセキュリティの課題のひとつだと痛感しました。
参加者の方々からは、
•「自分のセキュリティ対策は本当に十分なのか?」
•「次回は会社の取締役も連れてきて参加したい!」
•「パスワードの管理方法は、今のままでいいのか?」
といった具体的で前向きな質問が多く寄せられました。
それだけ関心の高まりと危機感が浸透し始めている証拠だと思います。
今後も警察当局や自治体と連携しながら、こうした実態を企業の経営層に伝え、「まずは知ること」「そして備えること」の重要性を広めていきたいと考えています。
ご協力いただいた兵庫県警察サイバー企画課の皆さま、ランサムウェアのデモをして下った警察庁近畿管区警察局兵庫県情報通信部の皆さま、そしてご参加くださった皆さまに心より感謝申し上げます。
一般社団法人中小企業をサイバー攻撃から守る会では、今後も中小企業を中心に、現場で役立つセキュリティ教育・研修・診断サービスを通じて、地域全体のサイバー防衛力向上に貢献してまいります。
2025.09.19 京都府警察とのコラボセミナー実施
先日9月19日、京都市内にて京都府警察サイバー企画課の方とのコラボセミナーを開催いたしました。
主催していただいたのは、一般社団法人Quadravita(https://quadravita.net/)。
Quadravitaが開催している一般社会人が社交の場でのマナーや礼儀作法、文化や芸術などの教養を身につけるための「クアドラ大学」の一般公開特別講座として開催をして頂きました。
また会場をご提供くださったのは、京都駅から徒歩約4分、7月24日にオープンしたばかりのハワイアンカフェ&バー「MahaloSKY」(https://mahalo-sky.com/)です。
おしゃれで雰囲気の良いMahaloSKYを午後から貸切で、なんと無償でご提供くださいました!
この場をお借りして、感謝申し上げます。ありがとうございました!
さて当日は、約50名もの方々がご参加くださいまして、スペース的にはかなりキツキツでしたが、みなさん熱心に聞いてくださって、「とても勉強になった」「知らない情報が多くて驚いた」「参加して良かった」などのお声を多数頂戴いたしました。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
また、ご協力くださった京都府警察サイバー企画課の皆様にもお礼を申し上げます。ありがとうございました。
今回は、ランサムウェアの詳細なデモをしてくださって、なかなか知る機会のない生々しいハッキングの様子を垣間見ることができました。また当会でも、来場者のメールアドレスに紐づいたパスワードが過去に漏洩していないかどうか、その場で確認できる体験コーナーも展開させて頂き、ご参加の皆様にとっては、まさに未体験ゾーンの連続だったのでは無いでしょうか。
全国の各警察当局との連携については、今後も継続してまいりますので、お近くで開催をする際にはぜひご参加ください。
2025.09.01 防災の日に考えよう〜サイバー攻撃への備え
「防災の日に考える ― サイバー攻撃にも“備え”が必要です」

本日9月1日は「防災の日」。地震や台風など自然災害への備えを見直す日として広く知られていますが、近年では「サイバー災害」にも備える必要性が高まっています。
実は先月、国内の自治体や企業を狙ったサイバー攻撃の被害報告が相次ぎました。特に目立ったのが ランサムウェア(身代金要求型ウイルス) による被害で、重要データを暗号化され、業務が数日間停止したケースもあります。自然災害と同じく「いつ」「どこで」被害に遭うかは予測が難しく、事前の対策が明暗を分けます。
ここで押さえておきたいのは、サイバー攻撃の「想定外」が日常的に起きているということです。
・取引先を装った不正メール
・AIで自動生成されたディープフェイクの音声や映像
・VPNやサーバーの脆弱性を突いた侵入
こうした攻撃は、中小企業を含め誰もが標的になり得ます。
では「備え」として、何から始めればよいのでしょうか。
まずは災害対策と同じく「基本の3ステップ」を意識することが有効です。
1. リスクの把握
どの資産(サーバー、PC、顧客データ)が守るべき対象かを棚卸し。
2. 対策の実施
UTM(統合脅威管理)を導入し、外部からの侵入や不審な通信を遮断。社員向けにはセキュリティ研修や不正メール訓練で“人の防御力”を高める。
3. 復旧の準備
バックアップの定期実施、インシデント発生時の対応ルールを明文化。
特にUTM(例:CheckPoint社製)は「防火壁」のように外部からの脅威を止める役割を果たします。自然災害で言えば堤防や耐震構造にあたる部分です。さらに、社員のセキュリティ意識を高める研修は「避難訓練」と同じ。どちらも欠かせない備えです。
「防災の日」の今日こそ、会社の“サイバー防災”を見直す絶好のタイミングです。
明日はあなたの会社が狙われるかもしれません。備えあれば憂いなし。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
無料相談はこちらから
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
2025.08.25 AI活用体験、1時間以上の作業がわずか・・・!
AIで業務の小さな手間を解決!
〜 動画合計時間を自動算出するアプリを作ってみた

先日、クライアントから依頼されていた情報セキュリティに関するeラーニング用動画データ30本を納品したのですが、「全ての動画の合計視聴時間を教えてほしい」と急に連絡を受けました。
1本ずつ長さを確認してExcelに打ち込んで合計する…そんな作業を想像するだけで気が遠くなります・・・
そこで「自分で計算するよりは、AIにアプリを作らせてみよう」と思い立ちました。
活用したのは対話型AIのClaudeで、要件を伝えるとすぐに試作品を生成してくれました。
最初のバージョンはうまくMP4ファイルを読み込めず、修正版ではエラー内容が表示されるようになったものの、時間計算が合わないといった問題が続出。それでも数回の修正を重ね、着手からわずか10分ほどで正確に合計時間を算出できるアプリが完成しました。
結果として、30本の動画の合計時間を瞬時に確認でき、作業効率は圧倒的に向上。
人手で1時間以上はかかるだろうと思っていた作業が、クライアントへの報告も含め、約12分で片付いたのです!(余った時間でこのブログ記事を書いてます笑)
こうした“小さな業務効率化”こそ、AI導入の第一歩として中小企業にもおすすめできます。
大規模なシステム導入や高額投資をしなくても、AIを活用することで日常のちょっとした手間を減らし、生産性を高めることが可能です。
ただし注意したいのは、AI活用にもセキュリティリスクが伴う点です。ファイルを扱う以上、情報の取り扱いルールや利用環境の安全性は必須です。業務でAIを活用する際は、「便利さ」と同時に「情報セキュリティ」の観点を忘れてはいけません。
AIとセキュリティは表裏一体。うまく組み合わせることで、企業の未来はもっと安全で効率的なものになります。
企業向け「情報セキュリティ対策×生成AI活用術」にご興味がありましたら、ぜひ一度ご相談ください!
無料相談フォーム(株式会社GatewayLink)
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
2025.08.08 AIによるサイバー攻撃!ディープフェイク・自動化攻撃の脅威
AIが攻撃側に?ディープフェイクや自動化攻撃に中小企業はどう備えるべきか
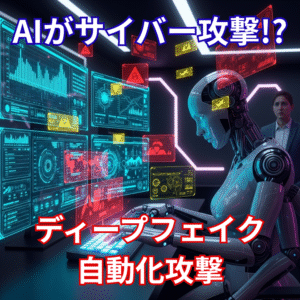
AIの進化は私たちの生活やビジネスを便利にする一方で、「攻撃者の武器」にもなりつつあります。
近年急増しているのが、AIを使ったサイバー攻撃、特に「自動化攻撃」と「ディープフェイク」による新たな脅威です。
■ AIが仕掛ける“自動化された攻撃”
攻撃者はAIを使って、フィッシングメールやマルウェア付きの文書を自動生成し、大量にばらまく「自動化攻撃」を仕掛けてきます。
たとえば、特定の企業に合わせた自然な文面のメールを何百件も短時間で作成し、個人名や役職まで自動で挿入することも可能です。
しかも、送信のタイミングや件名も最適化されているため、受け取る側は「本物だ」と思い込んでしまいがちです。
■ ディープフェイクで信頼を悪用する
さらに注目すべきは「ディープフェイク」の活用です。
これは、AIが人物の顔や声を本物そっくりに合成する技術で、すでに詐欺目的の音声通話などに使われ始めています。
たとえば、経営者本人の“声”を使って社員に「至急、取引先に送金してほしい」と電話をかける…そんな詐欺が、実際に発生しています。
映像付きでZoom会議を装われたら、見抜くのはさらに困難になるでしょう。
■ 対策のカギは「AI×人の目×訓練」
こうした脅威に対抗するには、従来のセキュリティ対策だけでは不十分です。
私たちが推奨しているのは、「AIによる攻撃には、AIで守る」という考え方。
たとえば、CheckPoint社のUTMは、未知の通信や不審な振る舞いをAIがリアルタイムに検知する機能を備えています。
“ゼロデイ攻撃”のような未知の脅威にも、高度な検知ロジックで素早く対応可能です。
さらに大事なのは「人の気づき」。
不正メール訓練やITリテラシー研修を通じて、社員一人ひとりが「だまされない力」を身につけていくことも必要です。
■ まとめ:備えあればAIも怖くない
AIによって進化した攻撃手法は、今後ますます巧妙になっていくでしょう。
「自分たちは狙われない」という思い込みこそが、最大のリスクです。
「何から始めたらいいか分からない」という方も、不正メール訓練のお試しやサーバー・ドメインの脆弱性診断など、小さな一歩から始めてみませんか?
感染したかも!と思ったら今すぐ迷わずご連絡ください。
また、セキュリティに不安のある方は、無料相談窓口へどうぞ
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
2025.07.28 AI攻撃が本格化!中小企業が備えるべき「人」のセキュリティ対策
AI攻撃が本格化!中小企業がいま備えるべき「人」のセキュリティ対策とは?
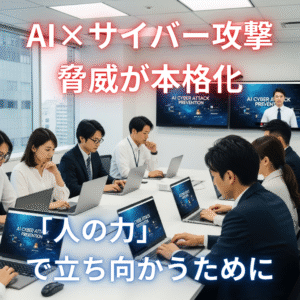
ここ最近、サイバー攻撃の手口がますます巧妙になってきています。
その背景にあるのが、生成AIの悪用です。
IPAが発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」では、組織に対する脅威として次のような項目が上位に挙がっています:
• ランサムウェアによる被害
• サプライチェーンを狙った攻撃
• 生成AIを使ったフィッシングやなりすまし攻撃の巧妙化
一見すると「ちゃんとした業務連絡」に見えるメールが、実はAIが作成した詐欺文面であった――そんなケースが増えています。
「人の判断力」が試される時代に
AIが自動で詐欺メールを作成し、音声までも偽造する。そんな中で頼れるのは、最終的には人の判断力です。とくに中小企業では、セキュリティ機器だけでは防げない攻撃にどう対処するかが課題です。
こうした背景から、IPAやNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)でも「人への投資」=教育訓練の重要性が繰り返し強調されています。
中小企業にこそ必要な“実践的な教育”
私たちが提供している不正メール訓練サービスは、実際の業務メールを模した“本物そっくり”の訓練メールを使って、従業員の判断力を高めるものです。訓練後はフィードバックも行い、「なぜ引っかかったか」「どう見抜けば良かったか」を学べます。
さらに、情報セキュリティ研修では、
• なぜパスワードの使い回しが危険か
• どのようなURLを踏んではいけないか
• テレワークで注意すべきポイントは何か
など、現場に即した内容をオンラインで提供しています。
特に、中小企業の経営者・管理職向け研修は、「社員まかせにしないセキュリティ運用の考え方」を学べると好評です。
最後に:AI攻撃に“人の力”で立ち向かうために
便利になったAIですが、それが悪用されるリスクもあります。
だからこそ、「技術」だけでなく「人の力」で備えることが、これからのセキュリティ対策では欠かせません。
不正メール訓練やセキュリティ研修は、企業全体の防御力を高める第一歩。
AI時代の“新しい常識”として、導入を前向きにご検討いただければと思います。
ご興味がありましたら、まずは無料相談を。
https://www.gatewaylink.co.jp/inquiry_free/
では今日もセキュアな1日を。
2025.07.24 不正メール訓練、押さえておきたい3つのポイント
ビジネスメール訓練は本当に効果があるのか?導入前に知っておきたい3つのポイント

中小企業における情報セキュリティ対策として「不正メール訓練」を導入する企業が増えてきました。しかし、経営者の中には「本当に効果があるの?」「うちの会社に必要なのか?」といった疑問を持つ方も多いのが実情です。
今回は、不正メール訓練の導入を検討する前に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
■ 1.開封率・クリック率の実態が“自社の弱点”を見える化する
訓練メールを開封・クリックする社員の割合を測定することで、社内のセキュリティ意識の現状が可視化されます。特に、役職者の開封率が高い場合、標的型攻撃のリスクはより深刻です。目をそむけたくなる数字が出るかもしれませんが、ここが改善の出発点です。
■ 2.単なる「脅し」ではなく、“教育”としての効果が高い
よく誤解されるのが、「引っかかった社員を責める」ための訓練ではないか、という点。しかし、実際には訓練後に丁寧な解説や研修を組み合わせることで、社員の理解度と注意力は確実に向上します。特に、実際の攻撃事例を交えたフィードバックは効果的です。
■ 3.定期実施で“気づく力”が育つ
不正メールは日々進化しています。年に1回の訓練では気づきの力は定着しません。最低でも年2回、できれば四半期ごとの定期訓練を通じて、「怪しい」と思った時に一歩立ち止まる習慣を根づかせましょう。
情報セキュリティ対策の中でも、不正メール訓練は比較的低コストで実施可能であり、非常に効果的な“守りの第一歩”です。
当社では、訓練メールの設計から実施後のレポート、そして社員研修までをワンストップで提供。価格も業界標準以下なので、低価格で効果がわかりやすいと好評価を頂戴しています。
気になる方は是非一度ご連絡ください。
では今日もセキュアな一日を!
2025.07.23 直近のサイバーインシデント事例、大手物流企業で障害!
大手物流企業で発生したシステム障害、その裏に潜むサイバー攻撃の影
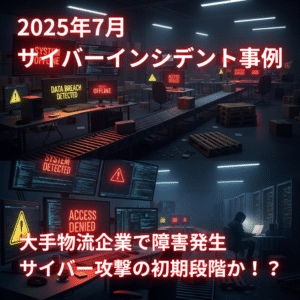
「システム障害」では済まされない、サイバー攻撃の兆候に要注意
2025年7月上旬、国内の大手物流企業にて配送管理システムの大規模な障害が発生し、一部地域で荷物の遅延が相次ぐ事態となりました。表向きは「システム障害」との説明がされていましたが、関係者筋の情報によると、外部からの不審な通信と異常なログイン試行が確認されており、ランサムウェア感染の可能性も含めた調査が進められているとのことです。
このように、企業のITシステムに起きたトラブルが、実はサイバー攻撃の初期段階であることも少なくありません。
なぜ物流業界が狙われるのか?
物流企業は「止まると困る」業界の代表格です。荷物の配送が滞ると、企業間の取引にも影響を及ぼすため、犯人側としては身代金(ランサム)を要求するにはうってつけのターゲットといえるでしょう。
また、サプライチェーン上の情報が集まるシステムは個人情報や契約データなども含まれており、金銭的価値も高い。こうした背景から、攻撃者にとっては非常に「おいしい」対象になっています。
中小企業も他人事ではない理由
今回の事件が大企業で起きたからといって、「うちは規模が小さいから狙われない」と考えるのは危険です。実際には、大企業を狙う前に、その取引先や委託先である中小企業のセキュリティの甘さを突いてくるケースも少なくありません。いわゆる「サプライチェーン攻撃」です。
特に中小企業では、メールを起点とした攻撃やVPNの脆弱性を狙う手口が主流となっており、UTMなどによる入口対策や、不審メール訓練といった地道な備えが今こそ必要とされています。
「気づかないうちに感染」は珍しくない
今回のように、障害の原因がサイバー攻撃であると断定できるまでには時間がかかることもあります。ログの確認や、アクセス権限の見直し、監視体制の整備など、日頃からの備えがあってこそ、迅速な対応が可能になります。
当社では、CheckPoint社のUTM製品を用いたセキュリティ対策のご提案や、万が一の際のインシデント初動対応支援も行っております。安心して業務を継続するために、今一度、御社のセキュリティ体制を見直してみませんか?
ご相談は無料です。どうぞお気軽にDMをお送りください。
では今日もセキュアな一日を!